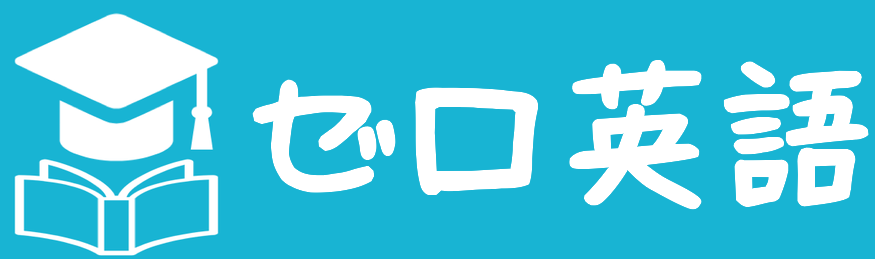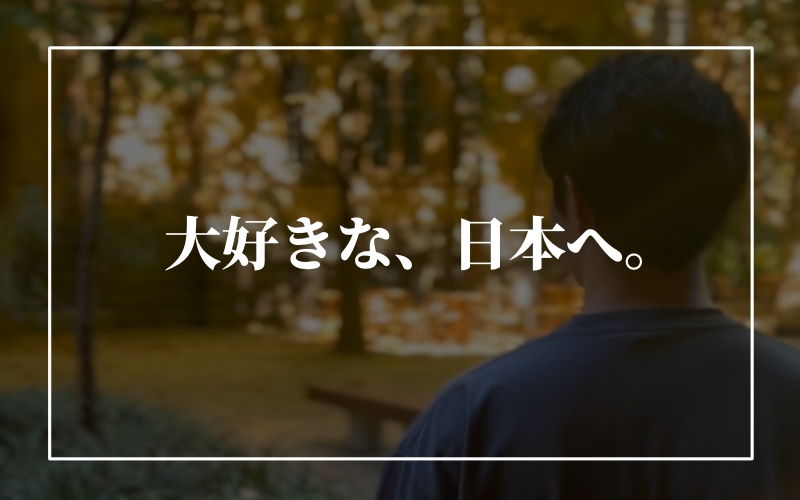この章では、20代の大半をオーストラリアで過ごした僕が、日本に帰国して率直に感じていることや今の感情を、僕の言葉で綴ろうと思います。
こんなことを言えばきっと怒られるだろうな、またSNS上で叩かれるだろうな、と、内心ビクビクしつつも、僕と同じように、ある種腑に落ちない違和感のようなものを抱えながら毎日を過ごしている人の背中を少しでも押せるものであれば良いな、と思い、これを執筆しています。
中には「日本のネガティヴキャンペーン」と捉えられる方もいらっしゃると思いますが(現にXでは多くの声を頂きました)、前提として、僕は日本が大好きです。人は暖かく、他人を重んじる文化が根付いている国は、他にあまりないと思います。
日本で生まれ育ち、日本をこよなく愛する1人の国民として、母国をより良い場所にしていきたいと考えているのですが、その際、外からの視点というのは有効である場合が多いです。僕は長崎で生まれ育ちましたが、実は地元の人ほど本当の地元の良さを知らなかったりします。内側から見るだけでは、自分の外側がどのような姿をしているのか見えにくいからです。
海外に出たからこそ、日本の素敵な部分やもっと素晴らしい国になるための改善点等、見えるものがあるのではないかと思うのです。
いろんな意見があると思いますが、これからお話する内容について、「確かに、変だよね」とか、「〇〇になったら良いよね」等、様々な議論が展開されるのであれば、震えながら執筆した甲斐があります(笑)。
ほんの些細なことでも良いので、「すごくわかる!」とか「もっとこうしたら良いかも!」等あれば、Xなどで「#ちーや論」とハッシュタグを付けてツイートして頂けると嬉しいです。すぐに飛んで「いいね」を押しにいきます。
消えないジョークと空気感

日本に帰国して最も最初に驚いたのは、他人の身体への言及がすごく多いこと。
久しぶりに会った友人に「太った?」と言われることは日常茶飯事です。それだけでなく、「肌、すごく焼けたね」とか、「何か、シワ増えたね」「目の下のクマ、すごいよ」といったコメントもよくあります。僕の心配をしてくれているとはわかりつつ、こうした指摘を聞くたびに、余計なお世話だよな、と感じる自分がいます。
服装に関しても、同様です。
時と場合によって着る服は変えた方が良い場合もあると思いますが、それ以外の場面では、誰が、いつ、何歳で、どんな服を着ようと、その人の自由です。
「その歳で、そんな派手な色?」とか、「その服、地味すぎ」といった声が聞こえてくることもありますが、派手な服装であろうが、パッとしない服を着ていようが、それを本人が良しとしているのであれば、それで良い。
誰にも迷惑はかけていません。
メルボルンの日常では、年齢に関係なく好きな服装で街中を歩いている人をよく見かけます。いろんな人種や価値観を持った人が同じコミュニティの中で共存しているので、どんな体型をしていても、どのような服を着ていても、誰も何も気にしません(もちろん、服装にはTPOはあります)。
宗教的な背景がある人もいれば、そのような体型を美德とする人もいるので、「そういう価値観もあるよね」と考えざるを得ないからです。

例えば、僕のホストマザーはギリシア人で、宗教上の都合上、数年間はずっと黒い服を着ていました。仮に僕が「もっと派手な服を着た方が似合うよ」と言ったとしても、「宗教上、これを行うことが習慣だから」と返答されてしまえば、それ以上言葉を重ねることは不要でしょう。
「なぜお墓に唾を吐いてはいけないのですか?」と聞かれたときに、「罰当たりすぎて無理だよ…」としか返しようがないのと同じです。
考え方や価値観が根本的に違う場合、「〇〇したら良いのに」という指摘は、ただの押し付けになる場合があります。
価値観や習慣は、それぞれの文化や信念に根ざしていることが多いので、他人が口を挟むこと自体がナンセンスであり、余計なお世話にだってなりやすい。
体型や服装も、誰かに見せるためではなく、自分が自分らしくいれるならそれで良いし、周りがとやかく言うことではないじゃん、と、思うのです。
日本では
『太った?』
『何カップ?』
『痩せたら可愛くなるのにね』
と、平気な顔で言う人がいますが、オーストラリアでそんなことを口走れば歪な目で見られ『来世で人生やりなおせ』と袋叩きにされる。
容姿なんてその人の自由なのだから、『ありのまま』で良いですよね。— ちーや🇦🇺ハーバードへ (@ChiyaMelbourne) June 22, 2019
日本においては、特に身体的特徴は冷やかしや嘲笑の的になっていることが多すぎるように感じます。
理由は色々とあると思いますが、その一番の要因は、特定の人を対象に笑いを取るお笑い番組やメディアの影響が大きいのではないでしょうか。日本のお笑い文化では、他人をいじることが笑いの一部として定着しています。身体的特徴や性格をネタにして笑いを取る場面が多く、意図せず他人を傷つけることを容認する文化を作り上げてしまっているように思うのです。
テレビを見ていて、時に過剰なくらい他人をいじり、その反応を楽しむことが多いなと感じますが、普段の生活においては、相手が「嫌だな」「不快だな」と感じる場合にも「冗談だから」と、片付けられてしまうことがあります。
(日本のお笑いはすごく好きですが)そういった点で、誰かをいじって笑いを作り出す流れにはすごく違和感を感じます。

僕が何よりも違和感を感じているのは、そのジョークをみんなが当たり前のように受け入れてしまう空気です。
誰かが傷付くようなジョークに周りが乗っかり、その場を盛り上げようとする状態が、こうした風潮を助長しているように感じます。対象になった人が納得し楽しんでいるのであれば、問題ないのかもしれません。いじられることでキャリアを駆け上がっている人はたくさんいるでしょうし、それが全て悪いことだとも思いません。
問題なのは、そのジョークが本人の許容範囲を大きく超え、他人の痛みや不快感を無視する場合がある、ということ。嫌だと感じていることに「No」と言ってはいけない暗黙の了解があり、そこに意見しようものなら、
「冗談が通じない」
「あの人は空気が読めないから」
と、その人のキャラやコミュニケーション能力が次の攻撃対象となります。
実際、日本で社会人となった僕も、同様のハラスメントを受けた経験があります。冗談がエスカレートし、それに対して真剣に不快だと伝えた結果、「冗談じゃん。空気読めないよね」と、逆に非難されてしまいました。
拳を振る側は、往々にしてその自覚はなく、むしろ反応した方が非難されるような空気になりがちです。

「空気が読めない」という言葉で、どれだけの人が歯を食いしばり、自分を抑え、心を殺してきたのでしょうか。ヘラヘラしながら自分の中で消化すれば、きっとその場はおさまるかもしれませんし、その場を取り繕うことで、周りとの摩擦を避けることができるかもしれません。
でも、いつまで我慢しなければならないのでしょうか。
一体、いつまで自分を押し殺さなければならないのでしょうか。
「空気を読めないお前が悪い」と言われると、自分が間違っているのかもしれない、という感覚になりますし、周囲の雰囲気に合わせることの方が正しいように思えてくるため、自分の内にある本当の感情や考えを押し殺してしまうことも増えていきます。
そして、少しずつ自分を見失い、本当は何をしたいのか、どう思っているのか、どうありたいのか、ということがわからなくなっていきます。

僕は、空気が読めません。それはきっと事実なのでしょう。空気を読めないことで迷惑をかけてしまうこともあるのだと思います。場の流れを壊してしまったり、誰かの意図をうまくくみ取れなかったりして、不快な思いをさせてしまうこともあるかもしれません。
でも僕は、嫌だと感じたことに蓋をしたくないし、強く「No」と言える人でありたい。
自分の意見を伝えながらも、周囲との調和を模索することができるのではないかと思っています。
空気を読むこと自体が悪いとは思いません。必要な場面もあるでしょうし、「和を重んじ、場を乱さない」ことは素敵な文化です。
ただ、その場が誰かの我慢で成り立っているのであれば、もはや「和」ではない。
誰かが一方的に負担を抱えるのではなく、全員が対等に意見を言い合える環境こそ、本当の『和』なのではないでしょうか。だからこそ、この問題は誰か1人の力で変わるものではなく、社会全体で「No」と言える空気感を作っていくことが大切だと考えています。
そのためには、「No」と言うことが尊重されるようなロールモデルや、具体的な行動を示す人が欠かせません。社会的に地位のある方や、会社の中で立場が上の人が、「No」と言って良いのだと発信する役割を担うべきでしょうし、そのようなモラルスタンダードを持った人がリーダーとして上に立ってほしいな、と思います。
僕は僕の目線で発信していけたらと思いますが、この文章を読んでいるあなたが社会のリーダーとなった際は、誰かが気持ちを抑えつけなくて済むような、素晴らしい組織・社会にしてくださることを切に願っています。